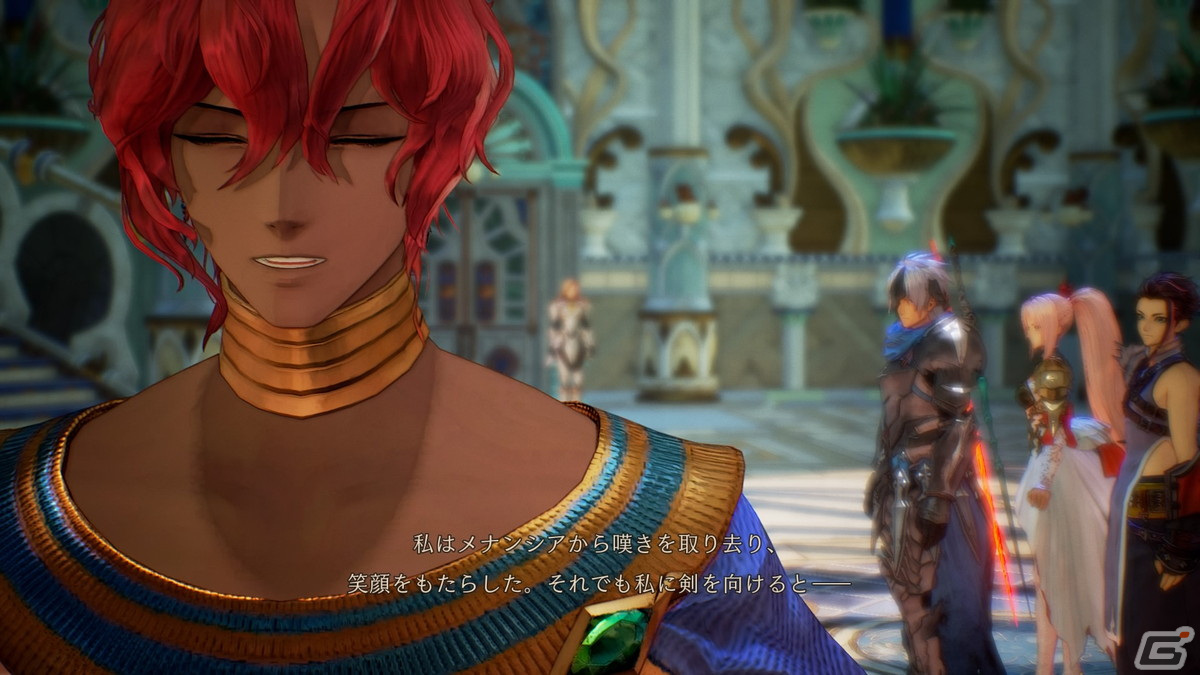バンダイナムコエンターテインメントより発売中のPS5/PS4/Xbox Series X|S/Xbox One/Steam用ソフト「テイルズ オブ アライズ」。発売後だからこそ聞ける開発エピソードの数々を、「テイルズ オブ」シリーズIP総合プロデューサーの富澤祐介氏、制作&マーケ担当のメインプロデューサーである玉置絢氏に聞いた。
目次
今回のインタビューでは、発売後ということもあり、立ち上げからの流れやプロモーション手法、そして筆者個人が気になった点まで幅広い質問に回答いただいた。大きなネタバレは無いものの、プレイしていないと分かりづらい箇所もあるので、読み進める際は気をつけてほしい。
「テイルズ オブ」シリーズの新たなマイルストーンを目指したスタート
――「テイルズ オブ アライズ(以下、アライズ)」の発売から約4ヶ月(※インタビューは1月上旬)が経とうとしていますが、現時点の反響に対する手応えや、ユーザーからの感想で印象的だった点をお聞かせください。
富澤氏:発売直後から非常に大きな反響をいただいたタイトルでもあったので、このお客様の熱というのをブランドとしてどんどん繋げていかなければなという思いを、僕個人としては新たにしているところです。予めの仕込みとしてはDLCや、スマホタイトルで今までにないスピードでパーティキャラクターの6人をコラボで登場させるという試みを、連続性をもった展開で行いました。
ゲームとしては1本完成されたものを遊びきってもらうという体験を目指しましたし、その上でキャラクターや世界観への興味といったものを2022年はゲーム以外のかたちでも広げていきたいという話はチームともずっとしています。
玉置氏:私は2019年の春頃から「アライズ」のプロデュースチームに途中合流し、ゲームの完成に責任をもつ制作担当として、また4月の発売日発表以降はマーケティングの担当としても関わらせて頂いております。ですので、「アライズ」というタイトルに強く手応えを感じたのは結構最近のことになってしまうのですが(笑)、発売前にYouTubeで公開いたしました「【Tales of ARISE】絢香『Blue Moon』 グランドテーマトレイラー」へ頂いたお客様の反応・コメントが特に印象に残っています。これは絢香さんの楽曲に乗せてストーリーの映像をピックアップした2分間の映像でして、もちろん発売前のPVですので本編の筋書きは読めないようにしてあり、要所要所のシーンをあえてランダムに散りばめた映像になっています。なので、ストーリーの展開自体はなんとなくの雰囲気でしかわからない映像なのですが、にも関わらずそれを見て「まだ発売もしてないのに泣いた」といったコメントを何個も頂きまして……。この時点である意味ホッとしました。「遊んでみれば良さがわかる」も大事ですが、「遊ぶ前から、キャラの顔や映像を見れば、心が動かされる想い・魂のような何かが伝わる」ことが重要だと思っていたので、「まだ買ってないけど泣いたわ」というコメントは非常に嬉しかったです。
あと、発売後にも意識する点として残っていたのは、キャラクターが愛され続けられるかどうかです。「ああ、いい話だった」で終わるだけでなく、遊び終わった後もキャラクターのことを覚え続けてもらえて、いろいろな場所で思い出し、楽しんでもらえるところに行けるかどうか。そして大きな変化を含んだ久々の新作である「アライズ」のキャラたちが、「テイルズ オブ」シリーズのこれまでを築いてきたキャラクターたちのファミリーに(お客様の心の中で)入れてもらえるかどうか、を非常に気にかけながら、IP全体に対する「アライズ」の関わり方や距離感を調整していきました。
私は「ソウルキャリバー」や「鉄拳」といった全く違うタイプのタイトルからゲーム業界に関わり、その後一番長く携わったのも「エースコンバット」でしたので、「テイルズ オブ」シリーズとは全く違う場所で仕事をしてきた人間ですが、子供の頃から親戚や友達に「テイルズ オブ」のめちゃくちゃコアなファンが多数いたので、ファンがいかに強い想いで各作品のキャラクターが歩んだ生き様すべてを大事にしているかと、等しく全ての作品のキャラクターが尊い存在として大事にされるべきだというファンコミュニティの空気、というのを身にしみて理解してきたつもりです。そういう実感をもっていた中で関わった新作が、これまでのシリーズ作品とはストーリーも見た目も大きく変わった挑戦的なタイトルだったので、開発チームと一丸となって送り出したキャラクターたちが、ちゃんと「テイルズ オブ」の新しい仲間としてファンコミュニティに受け入れられるかどうかを見守っていくのが非常にハラハラする時間でした。私はIP全体ではなく「テイルズ オブ アライズ」という一作品のプロデュース担当なので、よりそう感じたのかもしれません。
結果、発売されて時間が経ってクリアの感想などを寄せられる中で、多くの方が(これまでの「テイルズ オブ」作品のキャラたちと同じく)自作のキャライラストや掛け合い漫画を上げてくださったり、「他のシリーズキャラと『アライズ』のこのキャラが出会ったら、こういう話をするんじゃないか?」といった漫画まで描いてくださったりと、そういった二次創作も含めてキャラクターの魅力を楽しんでくださっているのが、非常に嬉しいです。ストーリーの枠を離れてキャラクターだけでも自由に楽しんでくださっているのを見て、しかも新作の「アライズ」の話しばかりではなく、様々なシリーズのキャラクターと等しく仲良く肩を並べている感じで扱ってくださっている方がとても多いのを見て、ちゃんと「テイルズ オブ」のファミリーに「アライズ」も入れてくださっているんだな……とすごく安心しました。
あと記憶に残っているのが、2021年のオンラインで行われた東京ゲームショウでのスキットコーナーです。シリーズのファンイベントではおなじみの「声優さんがその場で『スキット』(ゲーム中で仲間キャラ同士が交流する短い会話シーン)を演じてくださる」という演目の「アライズ」版が初お披露目になったコーナーなのですが、オンライン配信のチャット上でもキャラクターに共感した温かい反応を山ほどいただくことができました。これまでのファンイベントでこの「スキットコーナー」を応援いただいてきた姿と同じように「アライズ」でも盛り上がっていただいたのを見て、「ようやくここまで来れた」と感慨深かったです。単に一本のゲームとして出来が良かったからというのを超えて、キャラクターの新たな一面が見られること自体を心から喜んでいただけるところまで来たんだ、というのは安心したポイントですね。
――富澤さんがシリーズに携われるようになってから本作を立ち上げるまでの経緯や、ご自身の中で明確にクリアすべき課題として考えられた点をお聞かせください。
富澤氏:携わるようになったのは2016年からで、ちょうど「テイルズ オブ ベルセリア」の発売後という時期でしたが、明確にその時点での目標として捉えていたものはいくつかありました。
その一つが、「テイルズ オブ」ブランドとしてのお客様をこれからどう維持拡大していくのか、ブランドとしてどう運用していくのかという課題です。
それと共に、ハードの世代がPS3からPS4にちょうど本格的に切り替わる時期でもありましたので、過去作の延長上での作り方から、大きく進化を目指すべきタイミングにも差し掛かっていました。
そこでこれまで基幹エンジンとして今まで使っていたものをそのまま使うのか、あるいは選択肢として挙がっていたUnreal Engine 4にステップアップすべきなのかという議論も含め、ちょうど「アライズ」の立ち上げの時期にはいくつか検討しなければいけないことがありました。それはイコール、この後数年先に生まれる作品がやはりどういう未来像で、どんなお客様に向けたものなのかということを定義しない限りは決められない、という課題に向き合うことから始まりました。
ただ個人的にはそこにあまり悩みはなかったです。25周年が迫っていく中でお客様もどんどん成長されますし、人によっては卒業もされますが、20年を超えるようなブランドともなると新規のお客様がなかなか入りにくいというコミュニケーション上の課題も生まれてきます。ですので、なるべく次の作品というのは多くの方が入ってきやすい、参入ストレスのない作品を提供したいという思いは最初からブレずに強く持っていました。
最終的にかたちになった「アライズ」もそういう思いはかなり明確に表現できたかなと思っているのですが、ここはシリーズにおいて新しいマイルストーンになるような、ここがスタートになれるようなものにすべきだという想いは、自分自身の明確な目標として開発チームにも伝えていくということは心がけていました。
――開発に着手するまではかなり話し合いを重ねて来られたのでしょうか?
富澤氏:今回アトモスシェーダーというかたちでグラフィックを大きく進化させているのですが、その検証自体は2016年の段階で並行して始まっていました。絵的な進化をUnreal Engine4を使って取り組むということは初期から決断していましたし、アトモスシェーダーのプロトタイプは既に2017年あたりの段階でも非常に独自性のあるものになるという見通しはチームでも共有できていましたので、、具体的にどこまで鍛え上げるかということをビジュアルディレクターの岩本稔をはじめビジュアルチームでずっと検証を進めていました。
その一方で、コンセプトの部分に関しては、ストーリーの骨子も含めてどんな作品にしたいかという議論は2016年の後半から重ねていきました。例えば、ダナとレナという二項対立がありつつも、奴隷という立場でそれを覆していくような物語にしていきたいということや、そこにどんなテーマを込めていくかといった根本の部分についての基礎固めですね。同時にキャラクターのイメージを出していくというのは、やや並行しながら整合性を取れるような部分を探していく作業があるのですが、それらを大体半年くらいやっていたと思います。
――「アライズ」では“継承と進化”というテーマを掲げられていて、それはそういった議論の過程から生まれたものだとは思うのですが、開発への取り組みと、実際にユーザーに届けるゲーム内容それぞれに何を指したものだったのでしょうか?
富澤氏:ユーザーさん向けの言葉と開発チーム向けのテーマというのは必ずしも一致するものではないのですが、おっしゃる通り、今回は結果的に近いメッセージというものをプロデュース側からも双方に出させてもらったというところがあります。
その背景として、先ほどからも少し話しているようにこれまで通りの作り方やマーケティングコミュニケーションだけを続けていくと、どうしても将来に向けてブランドが先細りしてしまうという懸念はありました。新しいお客様にも届ける作品にすると決めている以上は、そのために必要なことを逆算的に行っていかなければいけないと。
これは既存のユーザーさんにとってみると不要に思えることに聞こえるかもしれないのですが、やはり作品やブランドを成長させるためには、常に挑戦し続けていく必要があります。5年に1本とかだったら余計にその姿勢が必要となります。ゲームという媒体はテクノロジーとも向き合っていかなければいけないですし、ゲーム性やキャラクターの側面で見ても絶えず挑戦を続けていくべきということは明確に実感しているところなので、そこは恐れずにやると決めていました。
とはいえ、ただ挑戦や変化だけを提供してしまったら、ブランドとしての価値を毀損してしまいかねませんので、どうバランスを取るのかというところになるのですが、そこのバランス取りの部分でも中間を取ってぬるくするというよりは2つの間で尖らせるというイメージで進めました。何を継承し、何を進化させるということを明文化し、開発側もお客様になぜこうしたということがロジカルに説明できるまで突き詰め、それができないような変化は絶対にしないという点で、制作からコミュニケーションまでブレれないようにやっていくことを意識してきました。
その具体的なポイントは多岐にわたっています。
例えばスキットは2D表現から3D表現へと大きく表現は変わったのですが、スキット自体が持つシリーズにおける根源的価値は絶対に変えません。「アライズ」で言えばゲーム全体において3Dモデルの表現力の圧倒的強化がもたらす統一性や没入感の維持といった、今までに無かった目標を達成するためにスキットも3Dモデルによる表現にしたのですが、そういった大きな仕様変更に際しての狙いもファンの皆様にプロモーションの中でしっかり説明し、ご不安を少しでも事前解消していただけるようなコミュニケーションにも取り組みました。
結果的には狙っていたような統一感を新たな魅力として感じていただけたこともあり、このようなチャレンジを丁寧にやっていくことの重要さを感じました。
そういったお話を一つ一つ積み上げていく上で、その軸として“継承と進化”というテーマを予めお伝えしていたという部分があります。そうでないとアレルギーも絶対あると思いますし、僕がお客様だったとしても、自分が好きだったブランドをあれこれ突然変えられたら「何で?」とは当然思いますので、そこに対しては目的と誠意を持って向き合っていかなければという想いは強く持っていました。
お客様と同様に、開発に長く関わっているスタッフにはじめにどう説明するかという部分にも苦労はありました。その時も「本当に3Dにするんですか?」と言われましたが、本作の狙いに理解を示してついてきてくれたスタッフには本当に感謝です。
――それこそ文化みたいなものですしね。
富澤氏:開発の中にも当然文化いうものがありますし、それをある意味壊しに来た人間のような立ち振る舞いを初期はせざるを得ない部分もありましたが、それでも理由をちゃんと説明して、覚悟を持ってその方向に行くならお客様が納得いくものにしようと開発も気持ちを良い意味で切り替えて、新しい挑戦に一緒に立ち向かってくれたというのがとてもありがたいことでしたね。
玉置氏:私は2019年からの合流で、そのタイミングには当然いなかったので、逆に客観的な目線で補足的なことをお話しますね。いざ関わるとなってとりあえず作り途中のゲームを遊び、そのあと富澤さんが最初に書いた企画書を見たのですが、本当に企画書通りの理想を目指して作られつつあるゲームがそこにはあったんです。それが何を意味しているのかというと、富澤さんの目指した「アライズ」の軸がブレてなかったということです。
大規模な今のゲーム作りにおいて、最初の企画書から完成まで軸がブレずに開発が進行するということは、けっこう珍しく、難しいことなんです。集団で作りますから、やはりこうした方がいいんじゃないかとか、ここで日和ろうといった意見も日々発生するのですが、そういったノイズは丁寧にカットして、やるべきことをやるというところで粘り強く関係者を説得されたのだろうなというのが、当時の時点で察せられました。特に今作はシリーズ作品とは異なる点が多数あるわけですから、それはもう色々な議論はあったと思うのですが、みんなで理想に納得して、ちゃんとそれを成し遂げるというところまでチームの気持ちが折れなかったというのが、「アライズ」がなんとか良い形で発売までたどり着けた最初の重要ポイントだったと思います。付き合い続けられた開発チームの実直さと志の強さと共に、最初からきちんと軸を整備してくれた富澤さんに感謝しています。
プロデューサーも人間なので、やはりみんながこう言うから変えたほうがいいかなとか色々あるのですが、そこに陥らなかったのは「ゴッドイーター」などでプロデューサーをされてきた人の貫禄だなぁ……などと、後から来て思っておりました(笑)。
富澤氏:僕はある意味、鈍感力を発揮する場面も出てくるんですよね。良い意味で「テイルズ オブ」ブランドにおいて僕は新参であったからこそで、僕も10年やっていたらこのジャッジをこのタイミングでできていたかは分からないです。ブランド全体の今後を任された以上はその責任をこのタイトルで果たさなければ僕の立ち位置は次作ではないだろうなと思いましたし。
発売まで長く開発期間がかかる中、お客様とも本来は作品を通じてコミュニケーションするべきなのですが、作品がまだ出せないうちは良くも悪くも潜るしか無いわけですよね。お客様の気持ちを想像しながらダイブする期間が長いと開発もそこで不安になったり、折れたりすることがあるのですが、結果タイトルを発表した後にプロモーションできない1年間があって、そこは開発チームも非常に辛かっただろうなと思いますし、自分自身も不安が募る時期でもありました。
過去の作品でいけば、それをテストプレイしてみたり、いろんな意見交換をユーザーさんとしながら、適宜改良していくようなゲーム作りの仕方を今までやってきたところもあったので、そういう意味での不安は無かったかと言えば嘘になります。とはいえ、こういう説明をすればユーザーさんに納得してもらえるはずだ、と少なくともロジカルに説明できるものを作っているはずなので、あとはどう伝えるかだと思っていましたし、ちゃんとお客様の前に出て真摯に話すという手法しか僕には無いのですが、「テイルズ オブ」でもそれをしっかりとやっていく前提で、その上で最後の責任を持つのは自分であるという覚悟は持っていましたが、ユーザーさんを信じるという点では楽観的に捉えてた部分もあり、周囲にあまり責任や不安を広げないようにしていったのは、ある意味ひとつの手法だったのかもしれないですね。
――今回はそれこそ、「ゴッドイーター」でずっとやられていたような直接ユーザーと会ってということがご時勢的にできなくなってしまったという側面もありましたしね。
富澤氏:しなかった部分とできなかった部分の両方があったかとは思いますね。「ゴッドイーター」に関してはシリーズとして、キャラクターや武器、アクションもある意味限りなく地続きで、様々な仕様をアップデートしながらシリーズを続けていくという作り方だったので、ユーザーさんの期待にミリ単位で応えるようなやり取りがある意味必須になっていったところもありました。
「テイルズ オブ」は今回のような挑戦かどうかは別としても、一作ごとに変える部分、新しくする部分があり、ある程度おおらかに次の作品というものを待っていただくという信頼だったり、ユニバースとしての楽しみ方があったので、そこはある意味お客様との前提というものを上手く活用しながら、「アライズ」も挑戦できたというところが当然ありますよね。
大規模開発ならではの体制づくりやプロモーションへの注力
――先ほどのお話にもありましたが、開発の過程で玉置さんが参加されることになった経緯についてもお聞かせください。
玉置氏:私が関わることになった理由は、簡潔に言うと「開発していくうちに、桁外れに規模の大きいゲームになりそうだと分かってきたから」です。
最初の企画書の時点から、「テイルズ オブ」を新しい時代・新しい世代にも愛されるシリーズにしていきたいという目的で企画された「アライズ」なわけですが、未来のためにそういったチャレンジをするという時点でもう、開発規模はこれまでとは比べ物にならない大きさになってしまうわけです。なぜかと言うと、長い歴史を持つシリーズタイトルでありながら、その印象をあえて一段階進化させたいといった挑戦をする場合は、「雰囲気が今のゲームっぽければ何でもOK」というわけではなく、それがシリーズを応援してきてくださったお客様の大半にとって納得いく正解でなければならないからです。この正解は誰も教えてくれなくて、実際に作ってコントローラーを握るまで正解とはわかりません。ですから、正解を引くまで何度も作り直すことが重要になり、開発には時間がかかります。さらに、2016年から2021年だと家庭用ゲームの市場環境も大きく変わっていて、どんどんワールドワイドのお客様からの期待も広く大きくなってきています。PS4の販売台数が何千万台みたいなのが日に日に更新されていくような状況だったわけで、それに応えるにも開発の規模が必要です。
そんな理由からどんどん規模が大きくなってきたという状況で、当初富澤さんがゴールとしているところにうまく着地するというのは、結構テクニックを伴うものでもありました。みんなが同じ方向を向いていても、日々の開発の中で綺麗に着地できないということはよくある話で、ディレクターはじめ開発者はみんな優秀なんですけれども、ここまで規模が大きいと段々まとめるのは大変になっていくというのもあるので、そこに助力が必要だというのがお話をいただいた理由の一つです。
正直に言って「アライズ」は、バンダイナムコエンターテインメントという会社の中でも、他に無いとは言わないものの、相当に大きなプロジェクトだったんです。もちろん、これまでのお客様のご支援と先人の方々の努力により、バンダイナムコにとっての「テイルズ オブ」がすごく重要なIPの一つになっていたからこそ、「アライズ」のような大勝負をやるという決断を会社一丸となって出来たわけですが、だとしても流石に「アライズ」の規模のゲームを作るのはなかなかレアな話しで、正しいスケジュールとしていつ頃に発売できそうなのかというのを予測することだけでも非常に大変なプロジェクトだったわけです。
じっくり時間をかけてちゃんとした正解をお客さんに出したいというところがあるにも関わらず、世の中の流行のスピードはどんどん速くなっていて置き去りにされるわけにもいかない中で、「アライズ」はどうすべきなのか……? という時に、開発経験のあるタイプのプロデューサーとしてお呼びがかかりました。それが2019年1月の「エースコンバット7 スカイズ・アンノウン(以下、エースコンバット7)」が発売になった頃です。「VRモード出てよかったっすねー」とか言っていた流れから継ぎ目なく参加しています(笑)。「エースコンバット7」もすごくでかいタイトルですし、その手前にもいろんなタイトルで(ありがたいことに、運良く)大規模かつワールドワイド向けのタイトルに開発者としても関わっていたこともあり、参加することになりました。
私がバンダイナムコスタジオの元社員で、「アライズ」もバンダイナムコスタジオで作っているのでそこに明るいというところもありました。あと、もちろんその当時はPS5やXbox Series Xの話などは意識していなかったのですが、「サマーレッスン」でのPS VRのように、新しいハードに序盤のうちに対応していくというノウハウも結果的に活かせてよかったかなと思います。
――予め必要な部分で関わったということもありつつ、結果的に世の中の流れに対しても上手く適応できる経験を持っていたということですね。
玉置氏:「サマーレッスン」や「鉄拳」で大恩のある上司だった原田さん(※「鉄拳」シリーズのチーフプロデューサーで知られる原田勝弘氏)から「玉置行ってこい!」という話がありまして(笑)。
富澤氏:そういえば、あの年は原田さんが我々の部長でしたね。
玉置氏:バンダイナムコエンターテインメントのオリジナルIPを原田さんが見る立場だったこともあり、上手いこと繋がりのあった人たちで上手くピースがハマったという感じですね。
富澤氏:そういう意味ではすべてが最初から狙ったような人材戦略が敷かれていたわけではなく、玉置が言ったように、バンダイナムコエンターテインメント、あるいはバンダイナムコスタジオの中で、ここまで大規模な家庭用ゲームの開発経験はそこまで多いわけでは無いからこそ、過去の経験を踏まえた人材をどう充てていくかというところが重要にもなってきます。「エースコンバット」から「テイルズ オブ」というとちょっと想像つかないですけど(笑)。僕も玉置が入ってもらった時に、まさにバンダイナムコスタジオとの経験を十分持っていてなおかつ元開発マンだというところでのプロデュース手腕にはすごく期待する部分もありましたが、それ以上に玉置はキャラクターや物語好きの人なんだなというのは、一緒にやり始めてからすごく知れたこともあり、「テイルズ オブ」にいい人材が入ってくれたなと思ったのを覚えています。
開発の後半から終盤をまとめ切るという部分では現場を筆頭で任せることができましたし、自分はブランドとしての25周年のタイミングが見えてきたので、そういったところへの仕込みを石川(※「テイルズ オブ」シリーズのIPプロモーターで、YouTubeチャンネルの管理人でもある石川結貴氏)をはじめとしたIP側のメンバーと設計していきました。そもそも「テイルズ オブ」のブランドロゴを作ったりといった、ブランドとしての整備もなかなか進んでいなかったところがあったので、2019年から2020年にかけてはそのあたりも洗い出して、来たるべき「アライズ」の発売や25周年に向けてのブランドの地ならしに注力させてもらったという点では、人材も厚くなってことで大規模な開発、あるいはブランド全体のコミュニケーションに初めて手が回ったという感覚は正直ありますね。
玉置氏:私がちょうどバンダイナムコスタジオの人たちと進捗の話をしている横で、確かに周年のロゴをどうするかという話をされていましたね。本の形にしようみたいなことを決めるかどうかの時期でしたよね。
富澤氏:「アライズ」のロゴデザインと一緒に25周年のロゴデザインのコンペをしていて、何を採用しようかという話を同時並行で進めていましたね。
玉置氏:参加した際に、「テイルズ オブ」を作っている人がそもそも「テイルズ オブ」を何だと思っているのかというのを最初に掴みたいなと思っていたのですが、ちょうどそのロゴの話をされていたんですよね。「やはり『テイルズ オブ』は物語だから本にしよう」という話をされていたのを聞いて、分かりやすく理解できました。「テイルズ オブ」って本当に色々な要素がてんこ盛りで、何か一つの要素だけを良さとして挙げるのが非常に難しいシリーズだと思うのですが、なんだかんだで一番最初に目を向けるべき要素は「感動できる物語」なんだなと。だから件の「買ってないのになんか泣けた」というコメントが私にとって重要だったんです。そういうことを周年ゆえにIP全体で考える状況だったというのが、結果的に良かったですね。
富澤氏:今までのロゴ(20周年のロゴ)はクレス(「テイルズ オブ ファンタジア」の主人公)がモチーフになっていました。25周年に向けては「アライズ」を意識していた部分が多分にあるのですが、新規のユーザーさんにもこのブランドのイメージを正しく伝えたいとなった時に、思い入れのないキャラクターが形になっていても入ってこられないですよね。クレスだと分かるのは「ファンタジア」をプレイしていただいているからで、新規の方にハチマキがたなびいている剣を持ったキャラクターがいても感情が動かないですよね。
このブランドは紡がれ続ける物語を通して感動を提供しているもので、それはキャラクターを通してのものだということは当然伝えるのですが、あえてキャラクター中心のロゴから物語を想起させるものに一回シフトチェンジしたというのも、細かい話ですが想定ターゲットへの伝わり方という点で狙いを持ってやっていました。
――話はずれてしまうのですが、昨年やられていた「テイルズ オブ リーディング ライブ」は、まさに物語を軸にして多くの人がいろんなことを思い返しているというのが印象的でした。
富澤氏:僕らもやはりキャラクターが先か物語が先かという議論をあえて思考実験的にすることもしょっちゅうあったりするのですが、おっしゃる通りキャラクターはお客様の中に入り込んだ後すごく大きなものになるのですが、その存在だけではなく、次なる物語があったり、キャラクターたちの新しい冒険だったりと何らかの語りがあって初めて生き続けるものになると思っているので、「テイルズ オブ リーディング ライブ」はそういう意味でも新しい試みとしては個人的に良いチャレンジだなと思いましたし、お客様の評価もすごく高かったですね。
懐かしのキャラクターたちによる新しい物語が、オリジナルキャストで紡がれるというのはなかなか普通ではありえないことですよね。ゲームでそれをやってくださいと言われると難しいことも多いのですが、だからこそ今回のようなチャレンジも生きてくるのかなと。やはりこれだけブランドが大きく、長くなっていく中で、ゲームだけでは全てをケアしきることは当然できない時代になってきてしまっているので、そういった時でも提供できるキャラクターや物語の価値というものはもっと目を向けていきたいですね。
――本作ではグローバルでの販売に意識を向けられているかと思いますが、プロモーションの観点からはどのように露出していこうと考えられたのでしょうか?
玉置氏:私が「アライズ」に関わった時点で、クリエイターの顔ぶれやストーリーの細かい筋書きまでは確定しておりましたし、世界中の「テイルズ オブ」ファン、および、「シリーズは知らないけど日本のアニメ・ゲームは好き」という世界のファン候補の方々にまで本作を届けようという展開方針は決まっていました。
それにしても日本で育ったシリーズをワールドワイドに展開するというのはすごく難しいわけで、何も考えないと、ただアメリカやヨーロッパのゲームを真似すればいいのか、という話になるわけです。これで上手くいかないことが多いのは、これをお読みの皆様もよくご存知かと思います。ではどのように展開していけばいいのか。ワールドワイド向けに多くのお客様が遊んでいただいているゲームに何本か携わらせていただいた経験が幸いにもあり、それをふまえて自分なりに「こうでなければいけない」という明確な確信というか信念をもって考えました。それは欧米のゲームをそのままコピーするというのとは逆の考え方で、「イラストタッチでライトノベルや漫画のようなストーリーが展開されるキャラクターを主体としたゲームが、なぜ日本の人にしか響かないという固定概念を持っているのか?」という問いでした。
こういうエピソードがありました。いまの部署に私が参加した当時はコロナ前だったこともあって、原田の肝煎りの方針で「現地のマーケターとは現地で打ち合わせしよう!」「視察に行ける海外イベントには可能な限り行け!」と言われまして。2ヶ月に1回くらいアメリカに出張するぐらいの勢いの時期がありました(笑)。そんなペースで「Anime Expo」や「New York Comic-con」に行ってクリエイターの方やファンの方と話したり、現地のアニメショップやゲームショップを見たり、アメリカの支社の担当者と話をしたりしていったのですが、「あっ、ゲームとか漫画とかの趣味において、本当に人種とか言語って何も関係ないんだ!」とすぐに確信できたんです。何をどう好きと語るか、その語り口とか雰囲気とかで直感的に「自分と同類だ!」と分かるというか、見た目と言葉が違うだけで、「魂」は本当に何も変わらないんです。ゲーム好き・アニメ好きの身近な友達と話しているのと同じようなノリで話せて、ただ言語が違うというだけなんですね。
確かに、地球全体で見たらそりゃイラストや漫画タッチのものをみんな好きというわけではありません。世界の中ではまだまだマイナーなジャンルかもしれません。しかし、世界規模で見るとゲーム市場そのものがすごく拡大しているというのがポイントです。これだけゲーム人口が増えたうえでの母数と掛け算したら、このジャンルが好きな人も相当数いるという計算になるんですよ。この方々にちゃんと伝えていくというのが重要だなと。
時代を追うにつれて姿や形はどんどん更新されていっても、根っこの心意気というのは変わらないよね、というのがまず大前提の想いです。ですから、世界に向けて展開するからといって、「テイルズ オブ」の根幹は変えてはいけない。なら、そちらではなく、むしろ「テイルズ オブ」が世界の人には刺さらないのではないかという不安のほうを打破して、先入観込みの課題を細かく拾い上げていこう、とマーケティング計画を立てました。そして、「テイルズ オブ」の良さのままで、世界中に「これは自分たちにとっての良い話だ、良いキャラだ」と思ってくれる人はいるはずだという読みを信じて、その人たちに伝わるように中身の伝え方とブランド的な印象づけを工夫していきました。
その計画づくりにおいて心強かったのは、日本の担当者の尽力はもちろんのこと、日本以外の各地域のマーケティングの担当者の存在です。彼らはビジネスマーケティングやプロモーションの専門家であるだけでなく、国は違えど普通にアニメが好き、ゲームが好き、「テイルズ オブ」みたいなゲームが好きという人々で、「うちの地元でそういう人に伝えたいなら、伝え方は任せろ」というプロフェッショナルでした。
バンダイナムコエンターテインメントという会社は、このIP以外にもいろんなアニメ・漫画をベースにした作品をたくさん手掛けているので、アメリカのバンダイナムコ(BANDAI NAMCO Entertainment America)やヨーロッパのバンダイナムコ(BANDAI NAMCO Europe)で一緒に働いている人って、やっぱりアニメや漫画を好きな人が多いんですよ。これが「テイルズ オブ」というIPを世界に広げていく上でラッキーだった環境要因です。ステレオタイプなワールドワイドゲーマー目線で何となく考えるのではなく、特にアニメとか漫画ライクな表現と物語のRPGが好きと思える人々に打ち出していくには……を具体的なイメージをもって構築していくにはうってつけの組織でした。
そんな感じでみんなアニメ・ゲームファンとして信用できるメンバーばかりだったので、今回の「テイルズ オブ」は地域の垣根を超えた一丸のチームでマーケティングしよう、と決めました。ですから、発売の2年前くらいからアメリカ・ヨーロッパ・アジアの各地域に作りかけのゲームを共有し、「遊んでみてどう思う?」という感想募集のコミュニケーションをずっと続けたんです。彼らから「テイルズ オブ」ファン、またはイラストタッチなRPGのファンとしてのフィードバックを色々ともらって耳を傾け、その中で確かにと思う指摘については改善採用したものもあります。彼らは普通にズブズブにアニメやゲームが好きな人々なので、いわゆる「洋ゲーみたいにしろ」といったフィードバックとかではなく、正しく評価した「テイルズ オブ」好きなアジア人、ヨーロッパ人、アメリカ人としての意見が返ってくるんです。
そういうやりとりをクッションに「何が好きか」を「似たものファン同士」の目線ですり合わせた上で、各地域の個別の事情にあわせた具体的なマーケティングを組み上げていけたのが、今回非常に良かったところではないかと思います。
もう1つのポイントが、YouTubeをはじめとした動画媒体の活用です。元々「テイルズ オブ」シリーズとしてYouTubeでの展開に取り組んでいて、私もほかのタイトルでもその強さというのを実感していたので、これを活用していこうというのがありました。
「テイルズ オブ」は物語とキャラクターのゲームなので、プレイヤーがゲームを通した様々な場面でどういう感情になれるかが大事なゲームだと思いますが、感情という切り口で言うと、短い時間で誰でも手軽に見られて、「このゲームはこういう気持ちになれるんだな」と直感的に分かるYouTubeのようなプラットフォームが最大限に活用できるタイトルではないかと。ネタバレへの配慮がもちろん重要ですが、トータルでは親和性が良いのではと考えました。
あと、YouTubeには国境はないんですよね。実際に動画のコメントを見ても、いろんな言語のコメントが付くんですよ。感情にも国境が無いので、いろんなところに住んでいる人に「普段なかなか味わえない、こういう強い感情をもらえるゲームだよ」と広く一気に伝えられる点が重要でした。
「『テイルズ オブ』からもらえる感情でつながる」というのがYouTube活用のキーだったので、プロモーション映像のつくりもそれに最適化されています。今までですと、キャラクターにフィーチャーしたPVをキャラごとに作るというのが「テイルズ オブ」だと定石で、ほかのゲームでもPVは大体3~5本くらい作るというのが普通でした。しかし今回は、実写の人が出ている販促動画も含めると40本以上になっていて、その代わりに1本1本は短くなっています。この作戦に出たのは、5年ぶりに出る新作だけど、様々な角度から「感情」への共感を呼びかけて、それのどれかがお客様ひとりひとりの心につながれば、安心して久々に遊んでみる手助けになるのではないかと考えたからです。
特に、以前公式アカウントのプロフィールにも入っていた、最初のキャッチコピーである“RPGよ、希望を紡げ。”という言葉──これは日本のプロモーションチームで考えていただいたものなのですが、この言葉のもつ雰囲気や感情を色々な動画を通じて伝えたかったんですね。
「アライズ」のいち側面として「こんな現状の世界においてなお、希望を語れるゲームとは何か、それはRPGだ。RPGが担ってきたそういった役割を、今こそ思い出してRPGに触れ直してみてほしい」という想いがあるんです。
子供の頃って、RPGの物語がひとつの人生の指針というか、この先の人生に向けての希望を指し示してくれる存在であったと思います。そして大人になり、RPGがジャンルの一つにすぎない立場のゲームになっている中で、RPGはどういう存在なのか? ということを改めて振り返ってみると、やはり今でも「希望を持てる」とか「前を向ける」とか、あるいは一時の感動を味わえたりとか涙したり……といった方面にパワーを発揮するジャンルとして、すごく強い力を持っているということに、お客様と私達のみんなで気づいていきたいと。そしてこんな今の世の中だからこそ「RPGというジャンルって良いよね、いま我々に必要だよね」と最終的に思ってほしいとう思いがあります。これを言葉で語るとすごく長いので、直感的に動画という媒体で短く、しかし頻繁に伝えるのが最適だと判断しました。
ほかにも「共感」をテーマにしたつながりづくりの開拓にもYouTubeを最大活用しました。日本だとリュウジさんという料理研究家の方とのコラボがあったり、海外だとバーチャルYouTuberの人とコラボがあったりと、色んな所でのコラボレーションも含めて「テイルズ オブ」を知らない人や、キャラクターコンテンツは好きだけどRPGは最近遊んでいないという人まで射程に入れて、「こういう気持ち・感情になれるゲームっていいな、やってみようかな」という感情の塊をネットコミュニティ上に作って行きたかったんです。
本物の体験版のほうがゲームの中身はよく分かるんですけれども、一番気軽に誰でも感情を共有できるという意味で、今このタイミングにおいてはYouTubeというアプリは世界最強の体験版アプリなので、ここから入ってきてもらおうと。そして、実際に8月に出した本当の体験版に接続するというのが大きな作戦でした。
ちなみに、今回の体験版はすごくリッチで、普通に作る体験版よりもめっちゃお金がかかっています(笑)。発売してから結構経っているので触れてしまいますが、隠しボスがいたりとか、いろんな要素があり、最後にクリアした時におまけムービーもあります。ぜひまだ遊んでない方は体験版だけでもお試しください。
――プロモーションを始めてから場当たり的に展開するのではなく、発売に向けた意識の中で動画を展開し、そこから体験版への導線をつないでいくということですね。
玉置氏:ここまで大きなタイトルで、開発にも時間がかかっていたので、逆にそれをじっくり考える時間があったという感じですね。
また、シリーズという大きな存在と、新たな子供として生まれてくる「アライズ」というものの相互関係を考えてコミュニケーションするというのも重要なポイントでした。これまでの「テイルズ オブ」は結構なペースで出ていたので、製品とシリーズというものを分けて考えるということがそれほどなかったと思っています。しかし今回は5年も間があいていますので、これまでのシリーズ作品と「アライズ」の違いというものがどうしても気になってしまう。ここをきちんと誠実に説明して、どの作品が好きなお客様にも納得していただけるよう最大限努力しなければと思っていました。
「テイルズ オブ」シリーズを愛している歴の長いお客様と、私たち「テイルズ オブ」のメーカーとの間で確実に共通しているのは、このシリーズが盛り上がってほしいという想いです。好きな人が増えて、なおかつ自分たちも熱くなれると良いよねという部分での利害は一致しているんです。だからこそ、「アライズ」という新しいものが出る際には、このシリーズを盛り上げていける良い材料になるというところに共感してもらえるようなプロモーションでなければいけないと思っています。一緒に盛り上げていきたいと思えるように、これまでと変わったところも含めてとにかく嘘はつかないし、誠実に向き合っていこうと。
富澤さんも大変だったと思うのですが、「アライズ」がこれまでのシリーズと比べて変わる部分については、YouTube配信を中心にかなり向き合ってもらいました。どの層のお客様にどういう反応があるのかを考え、実際にお客様から意見を募集したりしました。中にはかなり厳しい質問もありましたが、これはシリーズのことを考えてこうなんだということをちゃんとカメラの前で富澤さんが話すと。このインタビューではいま私が偉そうに喋っていますけど(笑)、実際には富澤さんがカメラの前で喋ったことが重要で、これが今後の「テイルズ オブ」にとっても大事じゃないかなと思います。
富澤氏:発売前のユーザーコミュニケーションを今まで以上に深いところまでやるというのは、今お話にあったような番組とかでもやりましたし、さらに言うと今後はやはり発売後のユーザーさんの反応との向き合いというのもしっかりやらなきゃいけないなとは改めて思っています。
発売から3ヶ月は全体的な評価も良いというところで、プロモーションもそれを糧にさせてもらいながら、たくさんの賞をいただいていたり、そういった部分も含めてポジティブに展開できました。とはいえブランド全体で見た時にこのチャレンジがどういう結果を生んだのか、これを気に入ってくださった方とそうでない方がいるというのは当然理解していますので、発売後のコミュニケーションとしてそういった部分にも真剣に目を向けていきたいです。
今後ブランドが30周年に向かっていくという時に、そこへの期待に対して「アライズ」という作品をマイルストーンにして、我々はさらに良いものをこれからも提供していかなければいけないなと。良かったところだけでなく、もっとこうしてほしいと思ったところ、そして今までのシリーズに対して「アライズ」は何でこうなったのかというところに対して、我々が全てをしきれたかどうかは正直分かりません。発売前に説明できることはしきったつもりですが、発売に感じたみなさんのリアルな感情というのは全て次への糧になっていくと思いますので、そこに対して蓋をするつもりは全くありません。
「アライズ」は2021年9月の段階で我々が出せた一つの挑戦のかたちだったとは思いますので、次はこの作品を踏まえた上での新しい挑戦や改善が当然ありますし、我々はそれを目指しているということは改めて伝えていかなきゃいけないなと思っています。僕としてはやっと1つの作品を出せたからこそ、次の作品まではまだそれなりの期間がかかるかもしれませんが、ユーザーさんとのコミュニケーションができるベースがようやくできたんだなという感覚ですね。
やはりゲームは作品を出して初めて分かるものですし、口で一方的に言う分には何とでも言えてしまいますし、それを信じる・信じないというだけの話になってしまうのはフェアじゃないと思っています。本当は毎年コンスタントに作品を出してコミュニケーションできることが理想なのですが、やはり大規模な開発となる過程において仮に5年に1本だったとしても、その5年間、ずっとみなさんの声は何も聞かずに作るなんてことはもうこの時代にはありえないし、許されないことだと思うので、ここからの数年間というのはユーザーさんの意見とともに次の作品にフィードバックさせていけるんだと思うと、僕はすごく前向きに捉えています。
玉置氏:今のところ好調なのは、もちろん開発やマーケティングの関係者の努力のおかげでもあるのですが、「発売してもいないゲームだけど、まあ、ファンとして信じてやってもいいか」と多くのお客様が言ってくださったからこそだと強く思っています。
どんなプロデューサーやパブリッシャーの人間もよく判で押したように「お客様に一番感謝します」と言うので飽き飽きされているかもしれませんが、本当にそうなんだから仕方ないですよね(笑)。リアルなお客様の心理の流れとして、まだ発売されていない久々の新作に対して、見た目も含めて何やら色々と変わっているらしい、不安でわからないところはある……だけど、生の情報を対話も含めて聞いた上で、「発売前なのにダメなんじゃないかというのはやめて、面白そうかもと期待を持ってみよう、とりあえず体験版を遊んでみよう、発売を待ってみよう」と思ってくださったからこそだし、それをTwitterしかりYouTubeのコメント欄しかり、いろんな場所で仰ってくださっているお客様がいなかったら、「アライズ」の評判がこうはなっていないのは間違いなくて。「テイルズ オブ」の歴史のなかで先達のクリエイターの方たちが築き上げてきた信頼というものがあってこそですが、本当に個人的なご厚意でお客様が今回も信用してみようと思ってくださったからこそ、良い雰囲気の中で発売日を迎えられました。そこは本当に一番感謝をするところで、だからこそまだ恩返ししきれていないと思いますし、毎年「テイルズ オブ」が忘れられる年なんてないという、ずっと面白くて楽しい世界というのをどう作れるかというのが、我々ができる恩返しだろうと思っています。
今の時代に合わせたストレスフリーや、アクションRPGとしての現在地点
――ここからゲームの中身についていくつかお聞きできればと思います。過去のシリーズでは乗り物を手に入れてなどの移動が主でしたが、今回に関してファストトラベルを採用された意図はあったのでしょうか?
富澤氏:乗り物ではなくファストトラベルを採用したというのは一例なのかもしれないのですが、「アライズ」全体で感じていただきたかった点として、ストレスフリーな体験というのは、開発テーマの一つではありました。
先ほど海外のユーザーを意識して別に違うものは作ったりはしないという風に玉置からも話があってまさにその通りではあるのですが、やはりゲームデザインやユーザーさんの使う時間とかに対しての与える価値みたいなものは確実に20年前と今では違う感覚をプレイヤーさん自身が持っています。そこは良い悪いではなく大きく変わったものだと感じておりまして、この5年でみても変わってきたと感じています。
それもあって、これまでのシリーズ以上にストレスフリーを達成するために変化させた仕様というのは、ファストトラベルも一例ですし、他にもバトル後のリザルトで映像演出を毎回挟むのはバッサリとカットして、冒険しながら流れるボイスでそこを表現していくというかたちにしたのも地味に大きな決断でした。短い時間の中でどんな感情の抑揚をテンポよく途切れさせずに詰め込んでいくかという細かい部分の積み重ねで感じ方の違いを出していった部分になっています。
そのようにして意図的に圧縮した時間の中でどう感情を動かすかというところにしっかり意識を向けつつ、しっかりと「キャラクターを感じる」というテイルズらしい価値においては結果的にプラスになるようにするというのを目標としながら、あえて絞る仕様と増やす仕様というのをしっかり選択・集中させていきました。
もちろん、乗り物に乗りたい、空を飛びたいんだという感情があるというのは発売後にご意見もいただいていまして、それも重々理解はしています。ただやはり、冒険において空が飛べることによってできること、あるいはやらなければいけないことの影響範囲というのはユーザーさんの想像する10倍ぐらい、いろいろとやらなきゃいけないことがありまして。15年前のゲームと今のゲームで同じ空を飛ばすことの影響度というのはものすごく変わってしまっているということもあるので、ここはもう泣く泣くという部分も正直ありました。
乗り物に乗って、ワールドマップ的なところを俯瞰した目線で旅することへのニーズや魅力があるというのを否定するつもりはなくて、結果的にキャラクターの感情などをしっかりと描ききるためにも、今回はプレイアブルとしての乗り物は登場させず、その分ファストトラベルのかたちでゲームとしてのストレスフリーは提供して、旅自体がつまらない、飽き飽きするといったものにはならないように設計するように選択したということですね。
今後乗り物は出てこないのか、とか「アライズ」でオミットされたものが次回作以降も全部切り捨てられたんじゃないかという風にお感じになるファンの方も当然多いかとは思いますが、発売後に出てくるご意見に対してもきちんと向き合っていきたいと思っています。。次は乗り物も乗れて、ファストトラベルとも上手く連携できてというようなものにチャレンジすべきだとは当然思っているので、今まではこうだったのにという意見は次に向けてこそぜひいただきたいです。
――そういった取り組みがあったからだと思いますが、プレイ時間もRPGとしてはちょうど良いバランス感で、かつ密度の濃いプレイ体験だったなと思いました。
富澤氏:何もない時間というのをなるべく作りたくはなかったんですよね。もちろんダンジョンに行って戻る時間を大事だと思う心もあるのですが、そこに何も提供できないのであれば、その時間というのはただの無為な時間に感じられる方が増えているというのを時代性と考えると、そこは短縮してでも次へ、次へという感情を演出していくことが「アライズ」ならではの語りにはなっていたんじゃないかなと思います。
――本作のバトルはテンポ、戦略性ともに完成度の高い仕組みだと思いますが、その上で今後の課題として感じられている点はありますでしょうか?
玉置氏:アクションゲームも含め、いろんなジャンルのゲームに携わってきた中で、今回初めてアクションRPGというジャンルに関わりました。そこで今回どういう風に作り上げるか開発チームと一緒に話し合ってきた結果分かったのは、やはりアクションRPGは「アクションゲーム」でも「RPG」でもなくて「アクションRPG」という名前でしか語れないということで、この点にこそ悩みがあるということです。「アクション」と「RPG」という2つの要素があって両方不可欠なんだとなると、それぞれ単体だったら起きない問題が、セットになるといろいろ起きてきます。そして、「アクション成分」と「RPG成分」をどのぐらいのバランスで調合するのかがゲーム体験を決める最重要ポイントになるということです。
「アクション」と「RPG」の2要素について、「アライズ」ではどのような調合がなされたか。一番わかりやすいのが、ガードがなくてその代わりに回避があるということだと思います(編注:キサラのみガードを行う)。要するにガードという概念があるとHPの足し算・引き算が重要で、ダメージを食らってゼロになる前に回復しつつ、なるべくガードしてHPが削られるのを防ぎながらタイミングを見て攻撃するという流れになります。これはとてもRPG的ですね。一方そこが、ガード主体ではなく避け主体ということになると、もっとアクション寄りの話になってきて、このタイミングで避けたらカウンターで攻撃して、さらにカウンターが上手く決まったらさらに違う敵にも飛んで攻撃という感じになります。このアクション的に流麗な操作体験が「アライズ」だと気持ち良いところになっているのは、ある程度の時間遊んでいただいた方には理解していただけるかと思います。
回避主体になったという例でもわかるように、RPG成分に比べてアクション成分をやや増しにしようという方針が「アライズ」最大の特徴です。いろんなゲーム業界の人の努力によって、「3Dのアクションは難しくないし、楽しくて気持ちいい」という印象を普段あまりゲームをやらない、非常にマスターゲットな人まで思えるような時代になってきている市場環境なので、新しいファンを増やしたい「アライズ」にとってこれはとても当然な方針です。
しかしながら、これをベストな形でデザインしきるのがすごく難しい。なぜかというと、「テイルズ オブ」には「仲間と一緒に闘う」という別の必要不可欠な要素があるからなんですよ。度合いを間違えて、あまりにもアクションゲーム化を推し進めていってRPG成分を薄くしすぎると、ゲーム的には仲間が要らなってしまうんですね。すごく有名な最近流行っているアクションゲームを想像してもらえると分かると思います。結構主人公が器用かつワンマンで強くて、パートナーのような存在がいなくはないですが、基本的には主人公がいろんな武器を戦闘中に使い分けたり、スキルを都度使ったりして繰り広げるアクションが多いですよね。でもそこに行ってしまうと、仲間は横からちょっと出てきて回復してくれるだけでいい、むしろそれ以上は邪魔な存在だとなってしまう。それは「テイルズ オブ」の行き着く先とは違うよね、と。
「テイルズ オブ」にとってバトルは何のためにあるのか、といったらむしろ順番が逆ではないかと。いろんな開発者の方とお話したのですが、「テイルズ オブ」とはキャラクターを好きになれるゲームであるという定義がまず先なんだなと感じました。その上で、じゃあバトルではキャラクターがどういう風に生き生きと活躍できて、それと自分がどうシンクロした気持ちで闘いに挑めるのか、バトルを楽しめるのか? という部分を、先達の方々は色々な手段で実現され続けてきたように思います。そして、それを最大化する最重要要素として「パーティーバトル」の概念が存在する。一回のバトルでも様々な仲間キャラクターの活躍をまとめて楽しめて、キャラクターの個性や仲間と助け合う心に共感し、みんなで勝利を分かち合える。そういう体験が作品ごとのトレンドよりも上位に存在することは間違いありません。
なので、仲間が引き立つようなRPGの要素はありながらも、カジュアルなアクションゲームとして気楽に遊べるよ、という部分を上手く融合させるにはどうしたら良いのかというのが「アライズ」の戦いだったと思いますし、まだまだやれることは多く、道半ばなところでもあります。
ただ今後も、「アクションゲームである」「RPGである」「パーティで一緒にバトルするゲームである」という3つを全部良い感じに成り立たせる、という難しい挑戦から降りて妥協することは絶対ないんだろうなと思っています。というのも、「テイルズ オブ」の開発チームの誰と話していても、みんなとにかく仲間というものに対する思い入れがすごいんですよ。このチームは、世の中全体のゲームをやっている人に対して「仲間と一緒に戦うゲームはいいぞ」ということを、声を大にして言っていきたい集団なんだなと。
じゃあ私達プロデュースチームはどう考えればいいかというと、一番の理想はこんな感じだと思っています……まず、いま一番市場でメジャーな「主人公が1人で活躍するタイプのカジュアルなアクションゲーム」全般を今遊んでいる人にも声をかけて、「面白いアクションが遊べるよ」という触れ込みで「テイルズ オブ」を初めて手に取っていただく。そしていざ遊んでみると「仲間が一緒にいるアクションって、このシステムだったら面白いな」となっていただく。ここはやはりアクション操作の気持ちよさと調和して溶け込んでいるパーティ共闘型RPGの要素があってこそです。そしてやがて、仲間と一緒に戦うのこそ楽しい、むしろこっちのほうが好き、という気持ちにまでなっていただき、最終的には元いた「1人主人公活躍型アクションゲーム」の分野に戻って遊んでも、「なんだか、仲間がいないとバトルの画面が寂しいな、また「テイルズ オブ」やりたいな」となる。ここまでの存在に到れれば、「テイルズ オブ」のバトルの目指す当面のゴールとしては理想ではないかと思っています。
「アライズ」でそれができているところは「ブーストストライク」や「ブーストアタック」かなと思います。これらはそれまであった秘奥義や術技の概念を拡張して、それらと同じかさらにワンボタンな仲間呼び出しアクションを用意したものです。アクションゲームのひと技として気軽に振っていける使い勝手を持ちながら、仲間とのコンビネーションを考えるうえではほんの少しだけRPG的な頭も片隅で使って楽しめる。2021年の正解はこれだと思いますけれども、この先「テイルズ オブ」がどうなっていくかを考えると、さらにアクションは気持ちよく、かつ仲間って良い、RPGって良いものなんだと思えるものにするという意味でのブラッシュアップはまだまだできるかなという風に思っています。
――パーティはそれぞれ操作できるものの、総合的にどう機能させていくかというところで、これまでは場合によっては主人公だけでやろうと思えばできるというものでしたが、今回は戦闘に直接参加していないキャラクターのことまでリアルタイムで意識する必要があって、それがすごく新鮮で楽しかったです。
富澤氏:6人全員が同時に出現はしていませんが、そうなっているかのごとく感じられる演出というのはブーストシステムできっちりと表現して、パーティアクションしている感じを今までとは一段上げたかたちで昇華できたというのは大きかったのではないかと思います。
その前提として、6キャラクターに明確なロールを設計するところから今回は始めたので、ある程度相補的なアクションがバトルをしていると必然的に誘発されるようになっています。敵もその行動属性によって効率が出てくるので、ここはテュオハリムに出てもらうべき、といったことがアクションの中で伝わっていくような設計を、シンプルでありながらも明確にしたので、そこが全てのキャラクターを遊んでもらうところへのモチベーションにもなったのではないかと思います。
開発者の目線でいくと6キャラクター分のアクションを全部設計しているので、遊んでもらわなきゃもったいなさすぎると思っているのですが、過去作で調査すると大半の人が主人公だけで最後まで進めたという感じになっているので、これは開発効率から見ても、これだけアクションを突き詰めていながら、ほとんどの人が体験していないというのをどうにかするべきだというのは感覚的にもありました。
今回の「アライズ」の発売後の調査を見るとバランスはもう少し平均化していますが、それでもアルフェンが一番使いやすいと思って素直にプレイされている方はまだ多いですね。2周目をやるときは別のキャラクターをお試しでやってみようとか、1キャラクターをメインで使ってはいたけどほかのキャラクターも使った気持ちに今回はなれたという部分が出たなら、それが「アライズ」としての成功の一つではあったかもしれませんし、その先を目指す縁(よすが)にもなるかなという気はしますね。
――そういう意味では、体験版でも全キャラクターを触れたのは良かったですよね。
富澤氏:普通のゲームの発想なら体験できるキャラ絞るんですけどね(笑)。
玉置氏:出し惜しみしろとか言わないよね、というのを各地域のマーケティング担当に説得して回りましたね(笑)。わざわざ体験版でキャラクター選択画面を作ったのは、アルフェンだけではなくてみんな使ってほしいというのがやはりあるからです。ストーリーの上では「この仲間が重要で、この仲間は重要じゃない」とかはないですし、6人みんな大事な仲間で上下はないので、ゲーム上でも上下があったり、重要じゃないというキャラクターをなるべく作りたくはなかったんです。
もちろん、人によってこのキャラクターのバトルスタイルが好みだったり、逆にあまり得意じゃないというのはあると思いますが、ゲーム側からは「全てのキャラクターに等しく操作されるチャンスがあって、バトル上でも愛される権利を等しく持っている」という風にご提供するのがやはり重要だったかなと思います。それに、仮にバトル上で苦手なことがあったとしても、ブーストストライクやブーストアタックとかいろんなところで、仲間のキャラクターともに連携できるというかたちで、みんな忘れずに公平に見てもらえるようにしたのが「アライズ」のバトルシステムですね。
――発売前にはかなり情報量を抑えられていたと思いますが、実際にプレイしてみるとダナの国々の多様性やダナとレナとの種族間の分断など、作中には今の世の中とも共通する問題が多数描かれていましたが、そうした要素を通して伝えたかったものはありますでしょうか?
富澤氏:発売前の段階では、すごく基本的な、かつわかりやすい部分でシンプルに構造のみをお伝えしていたというのは狙いを持ってやっていたことではあります。特に「アライズ」ではパーティの中にダナとレナという大きな対立構造の縮図のようなかたちで配置することによって、旅を通してずっとそのテーマについてパーティの中で考え続ける、語り合い続けるということにボリュームを割いています。
これまでですと、道中出てくる敵と思想対決をして、倒すけれどもそれが正しかったのかどうかを都度考えたりもするような語りの構造の作品が比較的多かったかなと思いますが、「アライズ」はどちらかと言うと敵はある意味乗り越えていくもので、その結果としてパーティの中で関係がどう変わっていくのか、考え方がどう変わっていくのか、パーティの持っている課題に対してどうやってもう一度向き合い続けるのか、といったところの語りが中心にくるような作りにしています。
その分、各国で描かれる多様な搾取の姿や分断のありようみたいなものは、本当にその世界の縮図であり、偶像化されたものももちろん多いですが、いろんな事象をこの6人が一つ一つ見て、彼らなりの考えを語り合ったり、考えを更新していくためのある意味舞台のようなかたちで5つの国というのを旅してもらおうと。
後半は本当にそれに対しての真相を語っていくなかで、ある意味分断や差別というものの根本的な無意味さみたいなものを表現していますが、差別や分断といった重い問題に対しての簡単な答えを提示するつもりはなくて、一つの問いかけのようなかたちでの展開が用意されています。現代では多くの方の中にも何らかの分断やマイノリティ感情があって、もがき苦しむことも多い世界の中で、簡単に単一の答えは出しようがないと思っていますし、どちらかに与すれば相手には別の感情があるというのは、今に始まったことではなくてずっと繰り返されていることでもあります。
何があれば乗り越えられるのかという答えを最終的にこの作品は出しているようで、完全な正解とはしていないとは思っていまして、それでも前を向いて一歩進む気持ちになれたり、反対側にいる人の感情ってどうなんだろうという風に語り合ってみたり、少し目を向けてみるという、そのぐらいのきっかけになればもうゲームとしては十分すぎるという感覚はあります。
「アライズ」という名前やジャンル名に“心の黎明を告げるRPG”というような言葉も使わせてもらいましたが、あくまで我々ができることはそういった問題に対して少し意識化するぐらいのところだと思っています。「アライズ」のエンディングが王道的で大団円を迎えたことに対してすごく良かったと言ってくださる方が多いのですが、最後は気持ち良く終えてもらいたかったところはあります。シオンとアルフェンは大きな課題を一つ乗り越えることで新たな環境を迎えられましたが、世界がそれで完璧になったかというと決してそうではないかもしれないというところも含めて、これからも彼らには成長や苦難というのはあるはずだと思っています。
これは「アライズ」に限らず、「テイルズ オブ」の作品はエンディングを迎えると全てが上がりというようなことではなくて、結局は新しい世界での次なる冒険や次なる課題、成長というものがずっと待っているものだと期待しながら、ゲームを1本終えてもキャラクターを愛する気持ちや将来に期待する気持ちを持ち続けてもらえるところがこのシリーズの大きな魅力だと思っています。そういう意味でも「アライズ」のエンディングも最大限気持ちよく終えてもらいつつ、更にその先に期待がつながるようにはしたかったというのはあります。
劇中歌にカバー曲を組み込んだ狙いとは?今後の展望も
――劇中歌で絢香さんがカバーした「Hello,Again~昔からある場所~」が使われていますが、ゲーム内で流れるタイミングが物語としても後半の大きな転換のところですごく驚かされた部分ではあったのですが、この取り組みに対する率直な手応えはいかがでしたか?
富澤氏:あそこは良かった、驚いたと言ってくださった方は多くて、狙いとしてはハマったかなという感覚ではおります。あとは「Hello,Again~昔からある場所~」という25年前の楽曲をカバーで使うというような手法も含めて、主に30代、40代の方々にやられたと言っていただいたけたのですが、僕も完全に同世代というところもあって、この楽曲設定には強い思いを持って取り組ませてもらいました。
既存曲に対する感情や若い頃の記憶ってものすごく強くて、それが「テイルズ オブ」だったかどうかは問わずとも、15歳ぐらいにやったゲームって多分一生忘れないでしょうし、多感な時の記憶を喚起するパワーというのは計り知れないものがあるというのは個人的にも思っていまして、そこに訴えかけるチャレンジでもありました。
「Hello,Again~昔からある場所~」をその歌詞も含めて物語の中にリンクするようなかたちで入れ込めたのは、この発想自体を初期から持っていたというのが大きいですね。シナリオが固まり切る前に今回はダブルオープニングで、かつ一つはカバー曲でやってみたいということで、なんとかぴったりの曲を探してくると言いつつ、その裏で僕は「Hello,Again~昔からある場所~」が一番ハマると思っていました(笑)。ただいきなりだと何を言っているんだコイツ、となってしまうので、いくつか案を出しつつも、自分の中ではすでに探索の時期を終えていて、確信的に「Hello,Again~昔からある場所~」が良いだろうと。そして絢香さんがカバーしていただけるということもありがたく決まったので、これは上手くいくはずだと。
となれば、OP2というような使い方だったり、その後の本編での使い方というのもなるべく効果を大きく発揮させたいと思いましたし、さらにはCMで使わせていただいたこともあって、過去の感情を換気させる効果も最大化できるだろうと。でも本編でこう使われていることは絶対伏せようということで、あくまでもこれはイメージソングのようにやっているんだなと一旦は思ってもらって、まさか本編でカバー使ってくるとは思わなかったという部分も含めて、サプライズ要素をそこに凝縮できるはずだというのは、多分にプロデュース的な目線でのアイデアでもあります。
ある意味僕の趣味嗜好も入れ込ませてもらって、開発チームにも納得してもらいながらできたことではありますが、毎回やると寒いので、次はまた別のさらなるサプライズを用意しないとなと思います。でもそのあたりで大体狙い通りの反応をいただけたのは、嬉しい部分ではります。
――にくいなと思うのが、CMで先に使用するなど100%隠さないところだなと。
富澤氏:「Hello,Again~昔からある場所~」のカバーについては、決めたのは2017年で、その段階でオファーをして2018年には決まっていました。最終的にCMに使ってくれるかどうかはプロモーション部次第だったりするのですが、「Hello,Again~昔からある場所~」を絢香さんが歌うというこの素材を使わないわけないよねという思いを持っていて、最終的に2021年になってCMに使うことが効果的だと言ってもらえて、ああ良かったなという感じでした(笑)。そういうイメージを自分の中で数年前の段階から持ちながらやれていたので、この思いがチームにも伝わって、お客様にも一番いいかたちで驚きを与えられたというのは、カバーを使うということの意味としては最大化できたかなと思います。
――「テイルズ オブ」シリーズにおいて本作を制作した意義をどう感じられているでしょうか?
玉置氏:先程申し上げたとおり、私は「テイルズ オブ」シリーズに元々携わっていた人間ではないのですが、2019年の春から途中参戦で関わることになった時にまず見たのは、実は「アライズ」の細かい開発状況とかではなくて、横浜アリーナで行われた「テイルズ オブ フェスティバル」というイベントなんです。
もちろん自分も遊んだことがあるし、友達とか自分自身の周りにも熱狂的なファンが何人もいたので、ある程度このシリーズのことを分かった気になっていたのですが、横浜アリーナでの熱気には次元の違うリアルな衝撃を受けました。本当に「テイルズ オブ」がめちゃくちゃ好きな人の集団というのがこんなにたくさんいらっしゃって、開演前から過去作のオープニングが1つスクリーンに流れるたびにすごい拍手と、それをきっかけに思い出話があちこちで始まるんです。こんなに好きな人が物理的に視界を埋め尽くす形でこんな人数いて、しかも演目の細かいところまで全部注目して、的確かつ温かい反応を丁寧に返して……という眼前に広がる大集団を目の当たりにして見て、「これはヤバい」と。何って、ここから「アライズ」という巨大で難易度の高い新作を期待に応える形で着地・完成させなきゃいけない立場になるという時にこれを見たものですから(笑)。急に関わったので悩みも迷いも色々あったんですが、とにかく「この人たちは絶対裏切れないな」と思ったんです。だから、どこまでいってもやはりこのシリーズはキャラクターや作品を丁寧に等しく愛し続けてくださる人の存在というのが一番中心にあって、この人たちとともにどういう未来に行くかというのを常に思って発売まで走り続けました。
「アライズ」をそういう意味で振り返るとき、本当に100%全てのファンの人に満足してもらえるものだったかというと、まだまだ道半ばかもしれませんが、シリーズを絶やさないための一本、今の時点で最大限トライした答えとして出させていただいたもの……という観点で意義があったと思います。
「アライズ」が出るまでの数年間の「テイルズ オブ」をとりまく雰囲気というのは、独特のものがあったと思います。長らく家庭用の新作が出ず、発売までのベールに包まれた時期も含めて、「テイルズ オブ」がどういう風になっていったら良いんだろうというのを、みんながそれぞれ頭の中で考えていた時期。そしてネットを媒介にしていろんな意見を出し合ったり拾いあったりして……メーカーのスタッフがお客様全員と本当に1:1で語り合うことは時間的にも難しいですが、間接的には全員が一緒に交流しながら、お互いにどういう未来であれば良いのかを考えていった結果として「アライズ」があったと思います。生きたシリーズであり続けるためには変わらないわけにはいかない、でもおかしな変わり方をして裏切るのは絶対にダメだ、ということですね。
長い歴史を持ち愛され続けるシリーズ特有の数多くの悩みを目の前にして、お客様と一緒になってこの先どうやっていけばいいんだろうと考えていくにあたって、「アライズ」という作品がこのタイミングに出たことは、良いマイルストーンになったと思います。新作が出ないのは一番嫌だろうというのはまず確信としてあって、でも下手な新作が出ても嫌だという風にも思われているんじゃないかという中で、このぐらいの「進化と継承」でどうでしょうかという例をお出しできたこと。そして、何を変えても怒られそうだからといって何も変えないことを良しとするのではなく、未来のための決断として変えた部分については、色々な事情で答えにくいことでも可能な限りちゃんと説明をして、このシリーズを良い形で続けていきたいという一緒の立場で粘り強く対話していく……というゲームの作り方、出し方というのがあっていいんだということが分かりました。結果ありがたいことに「発売前だからまだ確証はないけど、まあ信じてあげよう」と言ってくださるお客様までも多く居て下さったと。ここに至るまでの長い時間を通して、「いろいろな趣味嗜好や意見・立場はあるけれど、『テイルズ オブ』を今後も生かし続けたいという前向きな志では一致して、お客様もメーカーもなく、全員のコミュニティで『アライズ』という新しい基準のRPGを世に出せた」という共有の体験をお客様に作っていただけたことは、今後のこのシリーズにとって重要な礎になると思います。
富澤氏:意義は本当にいろんな側面で自分も打ち立てながらやってきたっていうところがあるのですが、冒頭に話した通り、「アライズ」でこれまでシリーズに触れてこなかった方や久しぶりに触れたよという方がこれまで以上に増えてくれたというのは、この作品をあえてこういうかたちで作って提供することの意義としては、ある程度果たせた部分もあるかなと思います。
一方で、今まで通りのものを求めていた方には違和感のある部分も実際のところはあったでしょうし、ブランド全体としては新規のユーザーさんが増えたから良いよという話ではないですし、これまで25年愛してくださった方含めて、一緒にブランドの未来へと向かっていけることが重要だと思っています。25年の歴史の中で自分にとってのベストタイトルというのは人それぞれでバラバラなわけで、その時の触れた年代や環境をやっていくことによって、それぞれにとってのマイベストがあって良い、好きで良いというのがブランド全体で見た時の「テイルズ オブ」のありようでなければいけないと。「アライズ」はその中の2021年に登場した一つとして好きでいてくれる方もいらっしゃれば、自分はやはりこの作品が好きという方も当然いらっしゃるので、そこを俯瞰したブランド運営というのをこれからもやっていかなきゃいけないなと感じています。
一作ごとには玉置が言ったようなそれぞれがやるべきチャレンジというものを臆せずにやっていくべきだと思っていますし、それが一個狙いとしてかたちにできた作品でもあったことには大きな意義があると改めて思っています。その上でブランド全体として提供するものが、「アライズ」のようなある意味我々としての最高の技術と努力をかたちにした家庭用のハイエンドというものだけが必要なのかというと、実はそうではないという視点をお持ちの方もいらっしゃるだろうと思っています。そのあたりも含めて「アライズ」が打ち立てたブランドの中の立ち位置が、全体を見た時にどういうもので今後もあるべきなのか、それ以外はどうするのかといったような俯瞰視点を改めて我々も持って、これからも続けて、あるいは広げていくつもりではいます。
そのための一つのマイルストーンとしての価値は、開発やプロデュースの目線からも大きな道標にはなりましたし、だからこそそれ以外のことも考えられるというありがたい環境に2022年は立たせてもらっているという意味では、この作品とそれを支持していただき、あるいはご意見をいただいたみなさんのおかげだと感謝しています。
――最後に本作をプレイしてくれたユーザーに向けてメッセージをお願いします。
玉置氏:ストーリーとしてはエンディングを迎えてはいるのですが、富澤からも話にあったように、まだまだあの世界にはいろんな展開があり得るだろうというものになっています。この先「アライズ」がどういう展開をしていったとしても、ずっとお客様の心の中にキャラクターたちが残って、ずっとあのキャラってこうだった、良かったという風に話し合ってもらえるような、いつの時代でも思い出してもらえると良いなと思っていますので、ずっと愛していただけると嬉しいです。
富澤氏:25年という大きな節目をまずは家庭用タイトルで提供できたことは、自分にとっては大きなスタートになったと思います。ここからやっとユーザーさんたち、ファンのみなさんとのほんとうの意味での対話を始められるんだなと強く感じています。
まずは「アライズ」をプレイしていただいて、良かったこと、要望含めて全てが我々の糧になると思っていますし、いずれの意見も無視できるものは無いと思っていますので、大きなタイトルとしての次回作もそうですが、例えば常々作品の移植やリメイクというものをファンの方々からご要望いただいており、自分にとってのマイベストタイトルというのは一生残っていくものだと思っていますので、それがプレイできない環境がこのブランドの中にあるというのは確かに良いことではないです。それこそPS2自体の作品のみで、自分がこんなに好きなのにプレイを進められる環境が無いのは決して健全じゃないという思いは共有していますので、全てをいきなりというわけにはいかないのですが、そのようなみなさんの気持ちにも応えていけるアプローチもブランド全体としては必要なのだろうと思っています。
そういう部分も含めて、2022年以降も30周年に向けて我々が一つ一つやるべきことというのを、「アライズ」を経て議論をしていますし、家庭用だけではなくスマホタイトルも含めたブランド全体で提供できるゲームやそれ以外の取り組みなどを通じて楽しみ続けられる、その上で好きだという気持ちに対して一つ一つ捉えていけるように、我々もまだまだ努力が必要です。それに向けてもみなさんのご意見一つ一つにある熱さや思いを自分たちなりに感じながらコメントを読ませていただいているので、良い意味で総合的に見ながら次の我々の一歩というのを一緒に描いていきたいと思っています。2022年はもうコミュニケーションの年だという風に我々も思ってやっていこうと思っていますので、ぜひお付き合いください。
――ありがとうございました。
Tales of AriseTM & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
※メーカー発表情報を基に掲載しています。掲載画像には、開発中のものが含まれている場合があります。
コメントを投稿する
この記事に関する意見や疑問などコメントを投稿してください。コメントポリシー